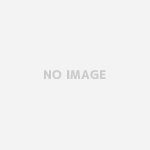敷き布団は寝心地はもちろん、寝姿勢、寝返りを支える快適性において大切な布団です。しかも、保温性や吸湿・放湿性の機能も持ち合わせる必要があります。
さらに就寝時に体の圧力がかかるので、かさ高さやふんわりといったコンフォータブルな要素は劣化しやすく、その上、汗や皮脂などの老廃物を受けとめるわけですから掛け布団よりもハードワークです。
セットで同時期に購入した掛布団の6割から7割程度の耐用年数だと言われています。
まず、耐用年数が近づいてくると、腰や首が痛くなるなど物理的に不快さを感じるようになってきます。普段から適正なメンテナンスに気を使い、カバーやシーツを複数枚用意して衛生的にご利用になっていても寝具の経年劣化であるヘタリや底着き感などはいずれ出てきてしまいます。
Contents
敷布団は寿命が短い!
販売の形態として、「〇点セット」や「〇〇一式」のように販売している場合も多く、特に掛布団と敷布団は買い替え時期もそろえたいとお考えになるでしょう。これを買い替えのタイミングとする場合、掛布団の大体の耐用年数を10年とすると敷布団は同じ材質の物でも7年程度で買い替えとなります。
また、毎日使用している布団は徐々に機能を喪失していきますが、毎日使用していると使用限度はなかなか解り難いものです。もちろん、耐用年数はあくまでも目安です。ですから、耐用年数が過ぎても特に寝心地に違和感を覚えないもあるでしょう。逆に、耐用年数前なのに朝起きると毎日、腰や首が痛い、布団が湿っぽいなどの症状がでる場合もあります。
いずれにしても、現在お持ちの敷布団の状況を把握することが大切です。そこで主な敷き布団の中素材別の耐用年数と寿命の見分け方をまとめてみました。
あくまでも目安ですので、判断が付かないようでしたら、一度専門店に相談するのも良いでしょう。
羊毛敷布団
寿命の目安
羊毛敷布団は購入当初から羊毛自体のクリンプやキューティクル状の構造によって引き締められ、かさ高は低くなります。その後少しずつかさ高は低くなっていきますが、表面の柔らかさはそのまま、体を支えるしっかり感ともいえる硬さはある程度あります。しかし、一方で吸湿作用もありますので、きちんと湿気が放湿されないと中心部からフェルト化が大幅に進行します。このフェルト化が進行して「干してもかさ高さが戻らない」「以前より重く感じる」「しっとりと湿気を感じる」「底着き感がする」という状態になります。この時に可能であれば打ち直しリフォームをお考え下さい。
羊毛敷き布団の寿命の目安 保温性が低くなりますので「寒く感じるようになった」り、弾力性を感じなくなる、中綿が偏って「ダマ」になります。全体的に硬い、重く感じるなどは機能の喪失または劣化のサインです。
耐用年数 5年から7年
羊毛布団羊毛ふとんの耐用年数は7年から10年ほどのようです。販売店のサイトでは3年から5年頭の意見もあります。業界のサイトでは5年程度との意見もありますが、利用者の意見では10年程度は利用しているとの意見が多いです。ふんわりとした包み込まれるような感触は3年程度、フェルト化するのが5年から7年というのが一般的な状態だそうです。もちろん羊毛の種類や質によってもかなり違うようです。7年以上になると通常のメンテナンスをしていても衛生的には心配になってきますので寿命としては最大7年程度での買い替えをおすすめします。
羊毛ふとんはクリーニングする場合はドライクリーニングを行います。打ち直しリフォームの業者もありますが、羊毛の性質上、ふんわり新品のようにはならず効果は限定的です。
また、長くお使いになるようでしたら、5年程度で打ち直しを考えることが良いでしょう。ただし、上記にも書いたように羊毛ふとんの打ち直しは効果は限定的ですが、衛生面では良いでしょう。(12.000円~)
木綿敷布団
寿命の目安
日干ししても柔らかさを感じなくなったら、もはや中綿が劣化しています。木綿は中綿の中でも回復力がある素材です。木綿敷布団はご使用になっていると繊維同士の絡まりが強くなってきます。それに加えて敷布団は身体圧や就寝時の湿気も加わり、この絡まりが促進されます。これにより、重くなったと感じるたり、中綿が硬く感じる、床面との底着き感がある、湿気が抜けなくなり、じめっとした感じがある、また、カビ臭や「なんとなく古いも特有の臭い」を感じたらそろそろ寿命を疑った方が良いでしょう。日常は日干しをして湿気を追い出すことにより繊維間の絡まりが改善されます。しかし、経年劣化や湿気とともに吸収される、体から放出される老廃物などにより復元力が弱くなってきます。
耐用年数 5年程度
10年程度、またはそれ以上ご使用の方もいるようですが素材の木綿の質、メンテナンスの回数によって寿命は延びます。国内産の一般的なもので、5年かもう少しご利用になったところで、打ち直しリフォームをするのが良いでしょう。大体、打ち直しは2回までが限度とのことです。木綿布団は長い間、多くの人に愛されてきた理由は、手に入れやすい価格であることも理由の一つですが、メンテナンスがしやすいことも人気の理由でした。放湿作用が他の素材より少し弱いのですが、定期的に日干しすれば衛生的でふっくらとなり、定期的に打ち直しをすれば長く使えることが大きな理由です。近年では「丸洗い」の業者も多く散見されますので布団店やクリーニング業者にご相談なさるのも良いでしょう。耐用年数は、使用環境や収納環境、メンテナンス(干す頻度・クリーニングの回数)などにより大きく変わってきます。
化繊・合繊敷布団
最もバリエーションが多く、評価することが難しいようです。化繊単独の素材としてはポリエステル繊維を利用したものが多いのですが、合繊と言われる他の羊毛や木綿などの天然素材と混紡し、中綿として利用される場合も多いようです。また、二層から三層構造で羊毛や木綿の中材と一緒に使用されることも多いのも特徴で、メーカー各社が特徴のある敷布団を製品化しています。
ここでは、化繊特にポリエステル繊維を多く使っているものについて言及しています。
寿命の目安
ポリエステルは加工することが容易なので抗菌・防ダニ・吸湿加工など様々な機能を付加されているものもあります。まず、この特殊加工の有効期限が一つの目安です。化繊・合繊繊維を使った敷布団を購入する場合はこの特殊加工のために選ぶことが多いからです。
また、廉価なものでは、1年程度でヘタってしまい床着き感を感じてしまうものや吸放湿性が低く、カビを発生させてしまうものもあります。これは、化繊・合繊自体がクッション性に富むようにつくられる場合が多く、下にマットレスを敷くなどの方法で利用される場合が多いためです。
また、重く感じるようになった、ヘタリが生じ、底着き感がある。さらには布団の内部から白い粉が出てくる、側生地が擦れている、糸がほどけているなど側生地の状態から寿命を読み取ることもできます。これは、通常、中綿の耐久年数以上持つような側生地を使わないからです。中綿の状態を側生地が表しているとも言えます。
耐用年数2~3年
化繊特にポリエステル綿の加工の種類抗菌防臭加工 黄色ブドウ球菌などの増殖を抑え、臭いを防ぎます。 制菌加工 菌の増殖を抑えます。 防ダニ加工 ダニを寄り付きにくくします。 消臭加工 アンモニア、酢酸、腐敗臭などの臭いを少なくします。 吸汗(親水)加工 汗などの水分を吸着します。 吸湿性加工 湿気を吸着します。 芳香加工 植物などの香りがします。 遠赤外線加工 遠赤外線を放射して保温効果を高めます。 難燃加工 燃えにくくします。 羽毛タッチ加工 独特のぬめり、風合いがあり洗濯耐久性に優れています。
ポリエステル綿100%と考えると2年から3年程度で交換する方が多いようです。これは調べてみると論理的でポリエステル綿に施されるさまざまな加工の抗菌加工・防ダニ加工・消臭加工などの有効期限が2年から長くても3年とされているからのようです。
もう少し敷布団の寿命を延ばしたい!
布団は「布団一式」「布団〇〇点セット」などといった販売形式をとっている場合があります。これは、「一式」や「セット」は、結構魅力的な値段だったり、インテリア的に統一感があったりしますが、各々耐用年数が違ってしまいます。特に敷布団は体重が長い時間掛かっていることや、体格や体質によっても劣化の度合いが違います。
ですから最初はセットで購入した寝具も徐々に個別に購入するようになるのが通常です。一度に大きな出費がかからないことを幸いとするのか、あくまで掛け布団との同時購入に拘り、敷き布団の寝姿勢の補正やの心地の改善のためにマットレスを購入するという考え方もあります。いわゆる低反発マットレスや高反発マットレスまたそれ以外のポリエチレン樹脂などのマットレスを購入して、補完しようという考え方です。また、オーバーレイやトッパ―と呼ばれるベッドマットレスの上に敷くベッドパットのようなものもあります。これらは大体の樹脂系のマットレスの寿命が3年から5年ですのでこちらを利用するのも理にかなった買い替えの仕方と言えますが衛生的に改善されるわけはありませんので敷布団の状態を見極めてご利用ください。