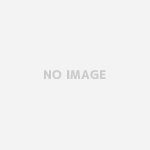寝室をベッドにしようか布団にしようか?
お悩み中の方はいらっしゃいますでしょうか。ベッドにするか布団にするかはそれぞれのライフスタイルのお好みによって決まることですが、最近の洋風化によって布団は劣勢になっています。
元々、和装寝具=布団は風通しの良い日本家屋で長年にわたり改良や進化を遂げたものです。布団を利用する環境は、高温多湿の気候で、木造の空気循環性の高い家屋とクッションフロアである畳が前提となっています。ですから、現代の一般的な住環境やライフスタイルを考慮すると夏の高温多湿の気候は同じでも最大の特徴である可搬性は生かせないのかもしれません。
Contents
敷布団の機能と選び方の常識を見直しました
「寝具として布団は時代遅れなのか。」という疑問からこのサイトは出発しました。
結果から申し上げると、快適な睡眠と寝具の関係や機能を見直すと布団は最も安全で清潔な睡眠環境を安価に構築できるものであると言えるのです。これにより、洋風の板の間に畳の就寝スペースを作ったり、ベッドの底板を畳にしてその上に従来の布団を引くというアプローチをしている方もいるようです。
これは、布団の可搬性を利用する定期的な寝具の日干しなどのメンテナンスのし易さ、就寝位置が低くなる安全性の特徴を利用したものです。さらに、布団の中素材(=布団の中の詰め物)を洗浄して入れなおしたり、経年劣化した中素材を新しいものに必要な量だけ交換する「打ち直し」をすることによって安価に機能を維持する事ができるなど、ベッドに比べ利点も多いのです。
敷布団の基本は2枚重ね
和装寝具である布団は収納することが前提で考えられています。敷布団はベッドでいえばマットレスと同じ機能です。軽くするために二枚に分割されていると考えていただければ分かりやすいでしょう。
この前提がなければきっと、早々とベッドの方が寝心地が良いことに結論付けられてしまいそうです。洋風化が進む現代でも4割以上の方が寝具として、和装寝具=布団を選んでいます。
敷布団一枚の重さに特に規定はありません。重いものでも7kgというのが大体の目安になっています。これは、力のない方でも持ち上げることのできる重さであると認識されています。
なお、ここでは便宜上、畳や床面側の敷布団を下敷布団、それに対し体側を上敷布団と言う名称としています。
敷布団選びのポイント
敷布団に焦点を当て大まかな選択するポイントを調べてみました。
最初に、自然な寝姿勢が取れれること。布団に入った直後の「フッー」と思わず口からこぼれてしまう安らぎ感。これがなければ良い布団とは言えません。特に敷布団は布団に入った直後の寝姿勢が心地よいかどうかが入眠・寝つきのしやすさに大きく関係します。
寝姿勢は個人によって様々ですが寝るときに好みの姿勢または、一番楽な姿勢を取れるという事が最初のポイントです。
敷布団の体圧分散と布団の硬さ・柔らかさ
次のポイントは、敷布団の柔軟性です。「布団は柔らかいもの」という連想は少なくとも敷布団に関しては適切ではないかもしれません。布団による肩や腰、お尻のコリや痛みはこの敷布団に原因がある可能性があります。
身体の一部分が不快な場合、その部分に体圧が集中している可能性があります。
例えば、柔らかすぎる布団をご使用の場合、身体が布団に沈み込んでしまい、就寝中の姿勢が不自然になったり、寝返りが上手く打てないので一箇所に体重の負荷がかかって、朝起きると体の一部分が痛かったり、痺れを引き起こしてしまいます。逆に、硬すぎる布団では、体の肩部・腰部・臀部に長時間体圧が掛かってしまい、これも痺れの原因になります。
敷布団には体を支えるための適度な硬さと、体型の凹凸形状により体圧が掛かってしまう部位の体圧を分散する柔らかさの両方を兼ね備えている必要があります。
畳や床との接地面の湿気対策
上下敷布団は同じ素材のものが一般的です。これは、2枚重ねで体を支えることと、体圧の分散を考慮しているからです。また、上下で入れ替えをして、長持ちさせることもできますし、交互に日干しするなどメリットもあります。しかし、必ずしも同じ素材である必要はありません。特に最近の傾向は、寝心地のために上敷布団をより上級ランクの敷布団にする、ウレタン系やポリエチレン系素材のマットレスを購入する方が多くなっています。
畳や床の硬さを感じる底着き感の緩和も敷布団の機能の一つです。それと同時に、特に下敷布団は床や畳から伝わる温度の遮断と上敷布団の温度差によって引き起こされる湿気対策の機能もあります。
朝起きたら布団と畳の間が湿っぽい、ひどいときには布団が湿気の水分でしっとりしていることもあるそうです。湿気を含んだ布団は日干しをすればいいのですが、毎日日干しするのは大変です。あまりにも湿気がひどい場合は敷布団と床の間に布団用スノコをお使いになるか、さまざまな防湿シートやマットがありますのでお使いになると良いでしょう。
年齢とともに適切な敷き布団は変わる
また、年齢とともに敷布団の適正も変化します。若いうちは多少硬くても柔らかくてもよく眠れるし、朝起きた直後、体が痛くても数時間すると気になら無くなる。という方もいらっしゃいます。
これはやはり若いからだとも言えます。多くの方が年齢を重ねると、「寝つきが悪い」、「何度も起きてしまう」、「朝起きると肩や腰が痛い」と、仰います。この原因が寝具のしかも敷布団が合わない場合に起こることが多いのです。
敷布団のおすすめの選び方
布団に入ったときに気持ちよく感じるもの
敷布団の最も重要な機能は睡眠に入るとき、布団に入った直後の寝姿勢が心地よいかどうかが寝付きやすさに大きく関係しています。
寝姿勢は個人によって様々です。仰向け・うつ伏せ・右下姿勢・左下姿勢・上半身を高くする・脚側を高くするなど、またこれ以外にもあります。
しかし、これから寝ようとした場合に好みの姿勢・眠るのに楽な姿勢で横になり、一定時間その体勢をとれることが入眠時の寝付きやすさに繋がります。
寝姿勢で選らぶ
多くの寝姿勢がある中で、すべての寝姿勢のパターン全てに対応した製品を作ることは非常に困難です。
やはり基本は仰向き寝(仰臥位=ぎょうがい)です。寝姿勢の中で最も多く、特に腰への負担が少ないとされる仰臥位。仰臥位の理想的な寝姿勢とは人間がまっすぐ立ったとき、背骨はなだらかなS字型を描いています。このS字型を保ったまま仰向けに寝た状態が一般的な理想の寝姿勢とされています。
そして、この寝姿勢を支えながら、一部分だけを圧迫することなく体圧を分散してくれるものが理想の敷布団です。
また仰臥位の次に多く、最近では寝姿勢としては最も良いとされている側臥位。横向き寝(側臥位=そくがい)の姿勢で寝る場合の敷布団の選択と仰臥位の敷布団の選択では違いが出てきます。側臥位で長時間寝ることを考えた場合、体圧のかかる面積が小さくなる分、より強い体圧が掛かることになりますので、仰臥位を基本とした通常の敷布団では体圧を吸収しきれず、肩の傷みが出てしまう場合があります。側臥位での理想的な寝姿勢は敷布団に寝た場合、背骨が水平になる姿勢が理想とされています。側臥位では特に枕の高さと硬さも重要な選択ポイントとなり、敷布団の一枚目・二枚目そして枕の高さを合わせて選択する必要があります。
敷布団は硬い方がいいのか?
また、敷布団は硬ければ良いというわけではありません。硬すぎる敷布団は、体圧を支える部分だけに負荷がかかってしまいます。特に腰痛に悩まれている方は注意が必要です。
さらに床面からの冷たさや底着き感を防ぐ役割もあります。この機能を一枚の布団で実現するためには、布団自体が厚くて重量のあるものになってしまいます。しかも、使用後は移動しなければならないので、2枚に分割する方法が考えられたようです。ですから、敷布団は2枚敷きが基本となります。
また、長時間体重を支えているものなので耐久性に優れたものを選ぶ必要があります。
中綿素材の機能と耐久性で選ぶ
中綿の素材は流通量が多い一般的な物でも羊毛・木綿・化繊・ウレタン系・ポリエチレン系・合繊(左記の素地を混合したもの)があり、またそれぞれ特徴があります。
さらに、寝姿勢の保持や体圧分散のために中綿素材を固綿化として圧縮し、中芯として利用しているものなど構造が違うものもあります。
敷布団は特に、毎日、全体重を支えているわけですから、寝具の中では最も劣化が早い物とお考え下さい。購入してから数日でへたってしまい、寝心地が悪くなるものもあります。また、羊毛敷布団のようにある程度固くなることは当初から予測してあり、寝ることに適した硬さを維持するように設定された寝具もあります。良い寝具は長く使いたいもの、寝具の耐用年数も考慮に入れて選ぶ必要があります。
布団の保温力は中綿の素材で決まります。敷布団は床面からの冷気を遮断する役目と床の硬さを感じる物(底着き感)は避けましょう。
敷布団選びのコツと補正のしかた
敷布団を選ぶ際には、保温性・吸湿性・放湿性も重要ですが、体圧分散や自分の体重、体格、寝姿勢に合ったものを選ぶことが重要です。
全ての面でご自分にピッタリの敷布団を選ぶことは困難なことです。最初は、敷布団でしか実現できない機能である長時間の寝姿勢の維持と体圧分散に焦点を当てて選択すると良いでしょう。これ以外の保温性・吸湿性・放湿性などは、シーツやシーツと上敷布団の間に敷く、パッド・オーバーレイマットレスなどに任せるという考え方もあります。
そして、何よりも大切なことは、敷布団だけは、お選びになる際は実際に寝てみて、感じてみてお選びになることを強くお勧めします。そしてその際には、必ず枕ご使用になってください。
寝姿勢や体圧分散は枕の高さや形状によってその性質や特徴が左右される場合が多いのです。
値段
やはり値段も重要なファクターです。寝具の価格は品質に直結していると言っても良いでしょう。やはり高額な商品は寝具として良いものが多いのが実情です。
しかし、敷布団の場合、最も高価な敷布団のセットがどなたにとっても最高の寝心地が提供できる物かどうかはわかりません。
「高価な布団は一生もの」との販売店の常套句がありますが、実際のところメンテナンスも何もしないで何十年も購入時と変わらない品質で使用できたという実例は聞いたことがありません。これは加齢とともに布団の好みが変わったり、体圧分散の重要度が増すことからみても懐疑的に考えざる負えません。
また、敷布団の値段は中綿の素材の品質と構造、側生地の品質が値段を決める要素です。特に敷布団は、寝る方の個人の体格や好みによって選ぶものです。高級素材の一点物を購入するより、普及品を購入して、自分に合わせてカスタマイズするという方法が良いでしょう。業界団体の品質基準や品質表示を根拠に購入することも賢い消費者の知恵です。
量産品の中には価格が安価でも、中綿が少なすぎて底着き感があるものや均一に詰められていないものも流通しているようです。以前に比べて悪質業者は少なくなったと言え、企業都合の商品を見抜く知識は必要です。
衛生とメンテナンス
手軽に扱えるというのも大きな特徴の一つです。
高級布団もいいですが、天気の良い日にはすぐに干したり、クリーニングに出せたり、打ち直しができるような手軽に扱える布団を選ぶのも賢い選択です。
快適な睡眠を得るには、衛生を保つことが大切です。手入れに手間のかかる布団は不衛生になりがちでこれも快適な寝具とは言えません。メンテナンスのしやすさも選択のポイントです。